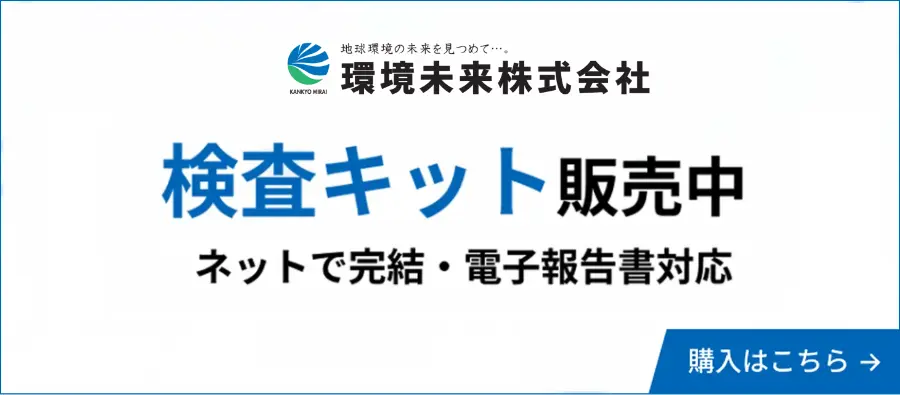検便

衛生管理の
検便検査
従業員の便中に赤痢菌、サルモネラ、腸管出血性大腸菌(O157等)などの有無を確認し、食品衛生法や各自治体の指導に沿った衛生管理を支援します。業種や規定に合わせて項目をカスタマイズ可能。大量検体・短納期に対応し、証明書付きの報告書を全国へお届けします。
腸内細菌(検便)検査
便中のO157、O111、O26、サルモネラ、赤痢、腸炎ビブリオ、ノロウイルス、カンピロバクター、コレラの検査が可能です。調理者、介護士、保育士が食中毒菌を持っていないことを確かめるための検査です。
腸内細菌検査は、症状が出ていない場合でも食中毒等の原因となる細菌を保有(保菌)している場合があるため、早期発見し、保菌者からの二次感染を未然に防止する意味で不可欠な検査です。
定期的に検査を行い、食中毒発生のリスクを低減させる安心安全な衛生管理が求められています。
対応可能な業種・施設
| 食品関連施設 | 食品製造工場・飲食店・給食センター・スーパーの惣菜部門など |
|---|---|
| 教育・福祉施設 | 学校給食・保育園・老人ホーム・障害者支援施設など |
| 医療・検査機関 | 病院・検査センター・研究施設など |
| その他 | 自治体の衛生指導や自主検査・イベント出店者の衛生管理など |
「大量調理施設衛生管理マニュアル」(厚生労働省)においては、大量調理施設の調理従事者などは月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。また、必要に応じて10月から3月にはノロウイルスの検査を含めることが望ましいこと」と記載されています。
「学校給食衛生管理の基準」(文部科学省。一部改訂:平成20年7月)には、学校給食従事者の健康管理として、「検便は、月2回以上実施されていること」と記載されています。
主な検査項目
- 赤痢菌:細菌性赤痢の原因菌
- サルモネラ属菌:食中毒の代表的な原因菌
- 腸チフス・パラチフス菌:発熱性腸炎などの原因菌
- 腸管出血性大腸菌(O157、O26、O111など)
- 黄色ブドウ球菌・その他の一般細菌(必要に応じて)
※検査項目は業種・自治体指導・社内規定などに応じてカスタマイズ可能です。
当社の特長
- 大量検体・短納期にも対応可能な検査体制
- 証明書・衛生管理記録として提出可能な報告書を作成
- 全国対応・定期検査や年数回の定期契約も可能
- 自治体・監査機関対応の検査基準に準拠
オンライン申し込み
弊社では全国の皆様がお手軽に検査できるようオンラインショップによる申込も受け付けています。申し込みによる検査も行っております。近くに検査ができるところがない方、業務が忙しいので効率的に検査を実施したい方など是非ご検討ください。
よくあるご質問
- なぜ検便が必要ですか?
食中毒菌に感染していても症状が出ない場合があります(健常保菌者、不顕性感染者と呼びます)。健常保菌者が調理を行ったり食材に接触することで集団食中毒が発生することがあります。検便検査はそのような「健康保菌者」を見つけ、食中毒の発生を防止します。
- 検便はどのくらいの頻度で行えばよいですか?
検便の頻度は、月一回が目安ですが、施設の種類によって異なります。
- 便を取ってから何日間保存できますか?
7日間保存が可能です。
- 生理中ですが検査可能ですか?
生理中でも問題なく検査可能です。(大腸ガン検査とは異なり、血液を検出する検査ではありません)
- 抗生物質を飲んでいますが大丈夫ですか?
抗生物質を服用している場合は注意が必要です。検査結果に影響が出るため、検査を控えて下さい。服用が終わってから数日空けてから検体を採取してください。
- チフス・パラチフスは含まれますか?
サルモネラ検査にはチフス、パラチフスAが含まれます。一般的な腸内細菌検査の結果書としてご利用いただけます。
サルモネラが陽性と言われました。対応を教えて下さい。一般的な対応としては、弊社が発行した結果書を持って医療機関を受診します。抗生剤の処方など治療をしたあと、再検査し、陰性の結果が得られたら調理などに復帰します。
- O157とはどんな菌ですか?
発症・重症化すると急性腎不全や溶血性尿毒症症候群(HUS)を引き起こし、死亡することもある危険な菌です。定期的な検査により、O157を保菌していないことを確認することが食品や介護、保育に携わる方にとって重要です。
- O26とはどんな菌ですか?
O157と同じように危険な菌です。下痢・血便を起こし、重症化すると溶血性尿毒症症候群や脳症を併発します。
- O111とはどんな菌ですか?
O157と同じように危険な菌です。下痢・血便を起こし、重症化すると溶血性尿毒症症候群や脳症を併発します。2011年のユッケなどが原因となった食中毒事件の原因菌の一つです。
- サルモネラ、チフス菌、パラチフス菌とはどんな菌ですか?
食中毒発生件数の中で上位を占める食中毒原因菌です。50%近いニワトリの腸管に存在する身近な菌です。サルモネラではとくに不顕性感染に注意が必要で、サルモネラに感染していても症状が全くないため、排菌しつづけるケースがあります。そのため、定期的な検査により、サルモネラを保菌していないことを確認することが食品や介護、保育に携わる方にとって重要です。
- 赤痢とはどんな菌ですか?
発症すると発熱、腹痛、血便、下痢を引き起こす病原菌です。重症化すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)、敗血症などを併発し死亡することがあります。
- 3項目でいいでしょうか?
一般的には3項目検査です。検査内容はO157、赤痢、サルモネラです。サルモネラ検査にはチフス、パラチフスAも含まれます。
現場、取引先によって5項目まで求められる場合がありますので、事前に確認してください。
なお、大量調理施設に該当する施設の場合(同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設 )、「調理従事者等は臨時職員も含め、月に1回以上の検便を 受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めること。 また、必要に応じ10月から3月にはノロウイルスの検査を含めること。」とあるので、5項目検査になります。
- 検査結果はどのように受け取れますか?
メール、もしくは通知書をお送りいたします。
衛生管理の基本は「人」から
検便検査は、従業員の健康状態を把握し、食中毒・感染症を未然に防ぐための最も重要な衛生管理の第一歩です。
当社では、迅速・正確な検査体制と柔軟な運用サポートにより、貴社の衛生管理業務を強力に支援します。